レンタル補聴器をお渡しする前にしていること 耳の穴に入る耳せんは、基本的に新品を使用しています。 耳の外側に触れる補聴器本体は、業務用の専用機器でクリーニングします。たとえば減圧乾燥機や紫外線滅菌装置などを使います。 もちろんレンタルの前には、新品同等の衛生状態かつ正常に動作することを確認していますのでご安心ください。 このほか、機械としての正常動作を確認するため、定期的にメーカーで分解点検を行っています。 耳に入れる耳せんは、新品をご用意しています 補聴器専用の真空乾燥機に入れています 補聴器真空乾燥機は、まず極細のバキュームで、音の出口の耳垢を直接吸い取りきれいにします。その後、真空に近い状態のカプセルに補聴器を入れることで、補聴器内部の汚れを強力に吸い取ります。 紫外線滅菌装置によるクリーニングを行っています 補聴器の表面に、もしも目に見えない細菌がいたとしても、紫外線滅菌装置で強力 […]
私たち大塚補聴器は、補聴器の専門家として、
一人ひとりのお客様に合った補聴器を選ぶお手伝いをしています。
補聴器に関してよく読まれている記事をまとめています。


レンタル補聴器は新品?使いまわし?すべてメンテナンス済みです

レンタルの補聴器には、どんな種類があるの?
また、補聴器の種類とは、形状の種類とメーカーによる音質の種類があります。 形状は、耳にかけるタイプの耳かけ型補聴器、オーダーメイドで作成し耳の穴に入れる耳あな型補聴器があります。 補聴器の音質は、メーカーによって大きく異なります。ご自分の希望や生活環境、または体質に合ったメーカーを選ぶ必要があります。 レンタル対象の補聴器の形 お貸出し用にご用意している補聴器は、耳かけ型補聴器になります。耳かけ型補聴器には、取り扱いが簡単な標準サイズと、目立ちにくい小型サイズ(RICタイプ)の2種類あります。どちらもレンタルのご用意があります。 標準サイズの耳かけ型 小型耳かけ型(RICタイプ) なおレンタルサービスの対象外になりますが、耳の穴に入れる耳あな型補聴器というものもあります。 耳あな型補聴器 ※オーダーメイド補聴器はお貸出しサービスが提供できない代わりに、お買い上げから90日以内は、無条件の返 […]

なぜ無料で補聴器の貸し出しを3ヶ月もしているの?
メーカーによる音質の比較 補聴器はメーカーによって、その音質が大きく異なります。ここでいう音質は、好みの問題ではなく、ご要望や生活環境またはご本人の体質との相性です。 音質の違いとして、言葉がハッキリ聞こえるメーカーもありますし、騒音を自動で抑えて快適性を重視するメーカーもあります。 何を重視するかによって、選択肢が変わってきます。 音質が合わないメーカーを選んでしまうと、どんな調整をしても満足いかないことがあります。 プロショップ大塚では、お客様のご要望をお聞きした上で、少なくとも2社のメーカーの補聴器を比較・体験していただくことをおすすめしています。 ご自分でメーカーの音質を聞き比べていただくと、自分に合った音質のメーカーを見つけることができます。1メーカーごとに1週間程度は、実際に使用していただき、自分で違いを確認していただきます。 形状による取り扱いと見た目の比較 補聴器は大きく3 […]

認知症のお客様から補聴器の相談があった際のご対応ポリシー
1,私たちの基本的な思い 不幸な補聴器の購入は、防ぎたいと考えています。よく聞こえないのに、お金だけを失うことは、お客様にとっても、私たちにとっても大変な損失だと思います。 お客様がお金を無駄にしないために、私たちが補聴器の販売をお断りするというのも、一つの対応だと思います。 しかし認知症であったとしても、人との会話やコミュニケーションを良くするための機会を、私たちの判断で奪ってしまうことが良いとも思えません。 ここに紹介する私たちのポリシーは、今までの経験から考えたものですが、完ぺきな正解とも思っていません。 ご意見、ご批判があれば、どちらもご連絡いただければと思います。 2,お客様の観察 高齢で認知症のお客様にもプライドがあります。自分のことは、自分で決めたいという気持ちがあります。 接客担当者がお客様を観察し、判断能力が十分と見込んだ場合、本ポリシーの対象になりません。 観察によって […]

OTC補聴器とは
OTC補聴器は、聴力検査なしで販売できる補聴器 OTCは、Over-the-Counterの略で、お店でテーブルにつかず、お店の人と立ったままやりとりするということです。 OTC補聴器とは遠回しな表現ですが「聴力検査なし、専門家のサポートなし」という意味です。 日本を除く、ほとんどの先進国では、補聴器の販売について強力な規制やルールがあります。これらの規制のため補聴器を販売するには、専門家による聴力検査や補聴器の音質調整などのサポートが義務になっています。これらのルールを守らず、補聴器を販売することは犯罪になります。 日本は先進国の中では、昔から補聴器に関する規制が少なく、聴力検査などを行わない通販の補聴器が合法になっています。amazon.jpでも、補聴器と検索すると、通販用の補聴器が数多く見つかります。 アメリカでは、2020年からOTC補聴器の販売ができるようになります 昔から日本で […]

集音器(PSAPs)と補聴器の違い
合法な補聴器と、脱法の集音器(薬機法について) 補聴器は、薬機法(正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)で定められた医療機器です。この薬機法の中で「身体に装着して、難聴者が音を増幅して聞くことを可能とすること。」(管理医療機器の別表2、361番および362番)と決められています。日本では厚生労働省などによって、効果と安全性について、管理されています。 これに対して、集音器は医療機器として必要な厚生労働省などによる管理や規制を受けていません。効果と安全性が確かめられていないということです。 普通の補聴器は、販売員による聴力検査と音質調整がセット 普通の補聴器は、一部のメガネ店や補聴器専門店で販売されています。普通の補聴器は一人一人の聴力に合わせて、音質を調整できるように作られています。通常、補聴器の販売価格には、聴力検査と補聴器の調整のサービス料が含まれて […]

補聴器にはベントという穴が開いているものがあります
補聴器の耳せんに穴が開いているのはなぜ? 補聴器をよく見ると、耳せんの部分に穴が開いているものがあります。 補聴器にはベントと呼ばれる穴が開いています。 これは、オーダーメイド耳あな型補聴器にも、耳かけ型の補聴器にもあります。 補聴器を耳に着けると、通常ならふさがれていない耳の穴をふさぐことになります。 人間は、耳の穴をふさぐと(補聴器から音が出ていなくても)、それだけで不愉快に感じたり、自分の声に違和感が生じる場合があります。 自分でやってみましょう! 今、自分で自分の耳の穴を、指でふさいでみてください。 この時、痛くない範囲で、ぎゅっと力を入れて、自分の耳をすき間なくふさぎましょう。 この状態で「あ、い、う、え、お」と大きめの声を出しましょう。 およそ80%ほどの方は、自分の声が大きすぎるように感じます。 同じ声の大きさで、耳の穴をふさいだ時と、ふさいでいない時を比べると、すぐに分かる […]

中耳炎経験者が補聴器を考えた時に気をつけること
治療が完全に終わってるか?治療による改善の可能性が無いことの確認 治療で回復すれば補聴器は不要 補聴器は難聴の方が使うものですが、難聴の中には、治療で回復する場合があります。 中耳炎が原因の難聴は、治療で改善する可能性がもっとも高い難聴です。特別な理由がない限り、基本的には補聴器の前にまず治療することがおすすめです。 中耳炎といっても、急性中耳炎、慢性中耳炎、滲出性中耳炎、真珠腫性中耳炎など、数多くの種類があります。1~2週間程度の短期間で治る中耳炎もあれば、治療に数カ月の時間がかかる中耳炎もあります。時間がかかる中耳炎の多くは、慢性中耳炎と呼ばれます。 特別に急ぐ理由がない限り、補聴器を購入するのは、耳の治療を先に完了させるのが良いでしょう。急いで補聴器を購入しても、治療で回復した場合、補聴器が不要になってしまう可能性があります。 なお中耳炎の治療が完了しても、聴力が完全には回復しない場 […]

補聴器から聞こえる異音の種類一覧、ハウリング、マイクノイズなど。
ハウリングによるピーピー音(フィードバックともいう) 原因 補聴器を使っていると、ピー!という音が聞こえる場合があります。これはハウリングとか、フィードバックとか呼ばれる現象です。耳せんにすき間が多いと、このハウリングは起こりやすくなります。 補聴器は、マイク(マイクロホン)に入ってきた音を、アンプで増幅して、スピーカー(レシーバー)から出します。この時、スピーカーから出てきた音が、すべて鼓膜に届いてくれることが理想です。 しかし実際には、音が耳せんのすき間から、耳の穴の外に漏れてしまうことがあります。音が外に漏れると、その音は再びマイクに入ります。 マイクに入った音が、また増幅され、スピーカーから出てきて、隙間から外に漏れ、またマイクに入る。この音がぐるぐる回ってしまうと「ピー!」という音が発生します。 この音がぐるぐる回ってしまう現象を、ハウリングとかフィードバックと言います。 耳せん […]

補聴器の専門家は、認定補聴器技能者と言語聴覚士
認定補聴器技能者の専門領域、資格の取り方、仕事の内容 認定補聴器技能者の専門領域 日本における唯一の補聴器の専門資格です。難聴の方の相談を受け、困りごとをお聞きし、ヘッドホンを使った聴力測定で状態を調べ、補聴器の調整を行います。補聴器の販売業務を兼任することも多くあります。 難聴の改善という意味では、耳鼻咽喉科の医師や、言語聴覚士とコミュニケーションを取りながら、補聴器の調整を行うこともあります。 耳鼻咽喉科の一部には、補聴器外来という難聴の対応を専門に行っているクリニックや病院があります。その中での役割分担は、医師は診察と治療および補聴器が合っているかの適合判定を担当します。認定補聴器技能者および言語聴覚士は、聴力測定、補聴器の調整、客観的な補聴器の効果の確認、取り扱いのサポートなどを担当しています。 難聴の相談については、どの職種が対応するかは施設によります。耳鼻科医師、言語聴覚士、認 […]
よく読まれている記事

キャッシュレス・消費者還元事業は補聴器も対象。しかも消費税は非課税!
2020年6月まで期間限定のキャッシュレス・消費者還元事業 キャッシュレス・消費者還元事業(キャッシュレス・ポイント還元事業)とは、10月1日の消費税増税にともない経済産業省が実施している施策です。 この事業に加盟した販売店で、お買い物するときにクレジットカードなどの現金以外のお支払い方法を選べば、お買い上げ金額の5%(もしくは2%)が、ポイントとして返ってくる制度です。クレジットカードの種類によっては、引き落とし金額が5%引きになることもあります。 還元率が5%になるのは、中小企業・小規模事業者だけです。コンビニなどの大企業での還元率は2%です。 (例1:普通のお買い物)5%還元のとなる中小企業の販売店で11,000円分(税込)のお買い物をすると5%にあたる550円分がポイントとなって還元されます。 (例2:補聴器のお買い物)5%還元のとなる補聴器専門店プロショップ大塚で300,000円...
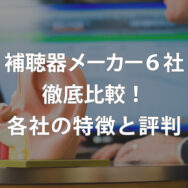
2025年:補聴器メーカー各社の特徴と評判、上位6社を徹底比較
補聴器の人気メーカーの比較と特徴 補聴器は一人ひとりの聴力を測定して、耳の状態に合わせて音質を調整するものです。しかしメーカーごとに調整で変えられない特徴があります。本記事では調整で変えられない特徴や評判を比較していきます。 多くの補聴器メーカーは、製品ブランド名と会社名が異なります。 本記事では、ブランド名を表記しています。なおカッコ内には国内の販売代理店ではなく、製品開発元の社名を記載しました。 オーティコン オーティコンは、北欧のデンマーク王国に本社を置く補聴器メーカー「デマント社」が展開する補聴器ブランドです。 オーティコンの補聴器は「Brain Hearing(脳で聴く)」をコンセプトに開発されています。デマント社は、耳だけでなく脳についても独自に研究を行い、その結果を活かして補聴器を開発しています。 2016年に発売されたOpn(オープン)シリーズから、他社とはまったく異なった...

補聴器を使った「聞こえのトレーニング」
最初は補聴器を正しく使いましょう 軽度~中等度難聴のほとんどの方は、適切に調整された補聴器を使用すれば、多くの場合、短期間で良く聞こえるようになります。 しかし難聴の種類によっては、正しく調整された補聴器を使っても、期待したように言葉が聞き取れない場合があります。 こういうケースでは「聞こえのトレーニング」で、もっと良く聞こえる可能性があります。 「聞こえのトレーニング」で良くなるのは脳!? 一般の方は、言葉を耳で聞いていると考えるかも知れません。しかし言葉の聞き取りに重要な働きをしているのは脳なのです。 耳から入ってきた音や言葉は、電気の信号となって神経を通り、やがて脳に届きます。そこで初めて言葉として理解されます。 難聴になり聴力が低下すると、脳に届く信号も弱まり、脳があまり使われなくなってしまいます。 人間の脳は何歳になっても使えば使うほど良くなりますが、使わないでいるとその働きが弱...
あなたに合った「聞こえ方」を
一緒に見つけませんか?


