伝音性難聴の特徴は(ほぼ)治療可能なこと 加齢などによる難聴と比べて、伝音性難聴は「耳の穴を強く塞いだような聞こえ方になるものの、大きな声はハッキリ分かる」という特徴があります。また治療で聴力が回復することが多いのも伝音性難聴の特徴です。 なお加齢などによる難聴の場合は「音は小さく聞こえるし、大きな声で話しかけられても言葉がハッキリしない」「大きすぎる音に強力な不快感を感じる」などの症状が加わります。 二つの難聴には大きな違いがあります。 伝音性難聴になる仕組み、原因になる病気、治らなかった場合の対策について紹介します。 加齢などによる難聴の原因はこちらをご覧ください。 耳には音を効率よく伝える仕組みがある 人間が音や言葉を最終的に感じ取るのは脳になります。耳には、脳へ音の刺激を効率よく伝える役割があります。 人間が音を聞く仕組みは、様々な器官の組み合わせで働いています。 ①「外耳道(耳の […]
私たち大塚補聴器は、補聴器の専門家として、
一人ひとりのお客様に合った補聴器を選ぶお手伝いをしています。
補聴器に関してよく読まれている記事をまとめています。


伝音性難聴と原因になる病気、完治しなかった場合の対策
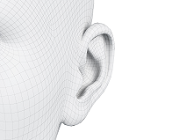
骨伝導補聴器4種類、特徴やデザイン、価格について
骨伝導補聴器とは?通常の補聴器と比べたメリット 骨伝導補聴器のメリットを理解するために、通常の補聴器と比べてみましょう。 通常の補聴器は耳の穴に入れたり、耳の上に掛ける形になっています。どちらであっても耳せんを使い、耳の穴を塞ぎます。音は、一般的なイヤホンやヘッドホンと同じように空気の振動によって鼓膜に伝わります。 骨伝導補聴器は、通常の補聴器と異なり、耳の穴を塞ぎません。また鼓膜が無くても聞こえる仕組みになっており、鼓膜を振動させません。骨伝導補聴器は、頭蓋骨を直接振動させることによって音を聞くことができる「骨伝導」という仕組みを利用しています。 骨伝導補聴器は、耳の後ろの骨に密着した部品(振動子といいます)から頭蓋骨へと音を伝えます。 骨伝導補聴器も補聴器の一種ですから、内部には振動子の他にも、音を感じ取るマイク、音を増幅するアンプ、これらが動くための電池などが入っています。 骨伝導補 […]

感音性難聴の原因と今日からできる予防習慣
耳の仕組みと、耳へのダメージ 耳は大きく分けて3つの部位(外耳・中耳・内耳)に分けられます。さらに、その奥にある蝸牛神経が、脳へ音を届けています。 耳の仕組み 人間が音を聞く構造は複雑で、さまざまな器官の組み合わせで音を聞いています。 ①「耳介」が音(空気の振動)を集め、効率よく耳のあなに音を届けます。 ②「鼓膜」が空気の振動を受けて震えます。 ③「耳小骨」が鼓膜の振動を蝸牛へ伝えます。 ④「蝸牛」は、振動(音)を電気信号へ変換し、神経を通して脳に伝えます。 感音性難聴の症状 難聴にはいくつか種類がありますが、ここでは感音性難聴でよくみられる症状をご説明します。 小さな音が聞こえにくくなる、音に気付きにくくなる 会話などの声は普通に聞こえるような方でも、体温計の音や時計のアラームなどが聞こえず、仕事や生活でお困りになる方がいます。 会話は一部聞こえない部分があっても他の音や文脈から推測 […]

補聴器技能者向けデジタルマガジン「イチからはじめる補聴器フィッティング」創刊!
このたび耳鼻咽喉科医師で聴覚評論家の中川雅文先生と、弊社代表の大塚祥仁による補聴器技能者向け共同マガジン「イチからはじめる補聴器フィッティング」がスタートいたしました。 中川雅文医師(国際医療福祉大学教授・同大学病院耳鼻咽喉科部長)は、世界中の補聴器技能者が最高の教科書としている「補聴器ハンドブック原著第2版」を監訳されています。 中川雅文先生のTwitterアカウント https://twitter.com/masafummi 補聴器ハンドブック 原著第2版 https://www.amazon.co.jp/dp/4263217489/ 補聴器ハンドブックは、補聴器技能者の教科書としてハイレベルで最高の教材なのですが、人は理論やテキストだけで学ぶわけではありません。初学者向けには具体的な事例や、かみ砕いた情報が必要です。 こういった思いで、中川先生と大塚が意気投合し「イチからはじめる補 […]

突発性難聴の症状は仕事や生活へどう影響する?対策と経済的支援
突発性難聴になった方で、元通りに回復する人は40%ほど。60%は難聴が残る。 厚生労働省の情報によると、突発性難聴は発症してから一週間以内に適切な治療を受けた場合、40%は完治します。50%の方は改善しつつも、元通りにはなりません。10%ほどは、治療の効果が見られないようです1)。これは発症してから一週間以内に適切な治療を受けた人の場合です。仕事などの予定のために、すぐに治療を受けられない人も少なくありませんから、突発性難聴の後遺症で困っている人は大勢いると思います。 米国のガイドラインによると、病院での治療が一段落しても難聴が残る場合は、残った聴力を活かし、様々な方法で生活の不便を補うことが推奨されています2)。対策は様々あるのですが、片耳だけが突発性難聴になった場合と、両耳とも聞こえにくくなった場合で対策が大きく異なってきます。 本記事では、少なくても片耳に、高度または重度の難聴がある […]

補聴器メーカー「ワイデックス(WIDEX)」の特徴と合う人・合わない人
補聴器メーカー「ワイデックス(WIDEX)」の歴史と音質の特徴 ワイデックスは1956年にデンマークで創業した補聴器メーカーです。2019年に同じく補聴器メーカーであるシバントス(旧シーメンス)社と合併し、社名はWS Audiology(ダブリューエス・オーディオロジー)社となりました。WS Audiology社は、大きな会社で、その傘下に多くの補聴器ブランドを持っています。現在のワイデックスは、製品ブランド名の一つです。 ワイデックスの補聴器は「遠くの声を、耳が良い人と同じくらいはっきり聞き取りたい」という難聴者の声に耳を傾け、開発されてきました。 その自然な音質と感度の良さから、ワイデックスの補聴器は一部の補聴器ユーザーから根強い人気があります。その証拠に、一度ワイデックスの補聴器を使用した人が他のメーカーの補聴器に買い替えるのはごく稀です。 ワイデックスの補聴器が合いやすい人は、会議 […]

難聴かも?テレワークでテレビ会議の聞き取りを助ける方法
テレビ会議には最新補聴器と音声認識アプリの組み合わせが最適! 「テレワークになってから、テレビ会議が聞こえない!」 コロナウイルス感染拡大防止のため、テレワークが始まり、多くのお客様から「テレビ会議で議論ができない、対面なら聞こえていたけどテレビ会議だと分からない。何とかなりませんか?」という要望をいただいています。 難聴の方は、日頃から相手の口の動きを見ながら聞こえを補っているので、テレビ会議で映像と音声が少しズレるだけで聞きにくくなってしまいます。 難聴の方が、テレビ会議に参加していただくためには、補聴器からテレビ会議の音声を聞き、同時にスマホの音声認識アプリを使うことが有効です。この記事で紹介する方法を使えば、補聴器からは周りのノイズなく、テレビ会議の音声だけが両耳で聞こえ、しかも高音質なので明瞭になります。もし発言を聞きとれなくても音声認識アプリが会話の理解を補ってくれます。 この […]

【コロナウイルス】感染拡大防止への取り組み(お客様と従業員の感染防止に最善を尽くします)
プロショップ大塚の衛生管理について スタッフは常時マスクを着用します。 店内では、スタッフは常時マスクを着用します。 口元が見えないと会話できないお客様の場合、透明マスク、フェイスシールドおよび筆談のご用意があります。 ご来店されたお客様には全員マスク着用をお願いします。 マスクをお持ちでない方はお渡しします。 ご来店されたら、まず消毒液をご利用いただきます。 スタッフも各所に消毒液を配置し、こまめに使用しています。 接客カウンターには、透明アクリル板をご用意しております。 完全予約制でご対応します。 当分の間、完全予約制でご対応いたします。 お客様同士で感染することを避けるため、お客様が同じ時間に重ならないようにいたします。 直接、店舗に電話で予約する 予約する店舗が決まっている方は、直接 各店舗に連絡をしていただくのが一番確実です。 パソコン/スマホから予約する 接客毎に消毒します。 […]

補聴器とスマホがアプリで連携する便利機能5つ
補聴器とスマホを連携する場合、スマホの器種によって制限があります。 iPhoneの場合「iPhone6S」以降なら、大丈夫。 iPhoneを補聴器と連携させる場合には「iPhone 6S」または「iPhoneSE(第1世代)」より新しい器種であれば大丈夫です。補聴器側にスマホと接続する機能があれば、アプリの機能がすべて使えます。ただし、スマホのOS(オペレーティング・システム)のバージョンは、必ず最新の状態を保つようにしていただくのが良いでしょう。 Androidスマホの場合、一部をのぞいて補聴器と接続する機能に制限があります iPhone以外のすべてのスマホは、Androidスマホと呼ばれています。Androidスマホの場合、ごく一部をのぞいて、アプリの機能に制限があります。制限がかかるスマホであっても、後ほどご紹介する「リモコン機能」「電池残量チェック」は使えることが多いです。 その他 […]

初めて補聴器を使うのは、いつから?専門家が勧めるタイミング
必要なのは聴力検査より専門家への相談。自分の状況をしっかり伝える。 難聴や聞こえの困りごとを感じた方の多くは、初めて補聴器を使うまでに平均4~6年ほど迷う期間があります。補聴器を始めるまでの間、インターネットで情報収集したり、耳鼻咽喉科などの医療機関に相談しています。 耳鼻咽喉科に相談すると、通常は聴力検査を受けます。ここで”聴覚が専門の耳鼻咽喉科”の場合、聴力検査の結果だけを見て「補聴器を使うべき」とか「まだ早い」という意見は言いません。 聴力検査の結果だけでなく、カウンセリングを重視します。そしてご本人が会話への困りごとを感じている場合、補聴器の体験を勧めます。これは相談者の70%ほどです。 難聴の原因が病気やケガなど治療可能だった場合には、補聴器を勧めません。先に治療することを勧めます。 専門家はカウンセリングで、始めるタイミングを考えている。 専門家によってカウンセリングで質問する […]
よく読まれている記事

補聴器購入に介護保険が使える?行政の補助はある?
介護保険が使えない理由は、厚生労働省 「補聴器は、高齢者に必要な道具なのだから、介護保険を使えたっていいじゃないか!」と思いますよね。私たちも、そう思います。そこで補聴器と介護保険、両方を管轄している厚生労働省の発行した資料を調べてみました。 介護保険を管轄しているのは、厚生労働省<老健局> まず介護保険について調べてみると、厚生労働省老健局が担当部署でした。そして福祉用具を介護保険に含めるかを判断する会議は「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」といい、なんと毎年開催されています。会議の結果によっては、もしかして補聴器購入にも介護保険が使えるのでしょうか? 介護保険における福祉用具・住宅改修の範囲の考え方! この検討会の中で、やはり毎年引用されている資料に「介護保険における福祉用具・住宅改修の範囲の考え方」というものがあります。補聴器購入の介護保険利用、せめて議論くらいされていて欲しいも...
難聴者が身体障害者手帳をもつメリットは?
難聴の障害者手帳を持っていて、お得なこと! 公共料金や携帯代金は半額以下または無料! 多くの携帯会社は身体障害者手帳を持っていると専用プランがあり、お値引きがあります。 また観光地の入場料や交通運賃も等級によって様々な割引があります。 NHK受信料 割引率:半額または全額免除 活用例:地上契約(継続振込等)月額が半額または全額免除 対象者:本人が世帯主で受信契約者の場合は半額、身体障害者手帳をお持ちのいる方がいる世帯で、世帯全員が市町村民税非課税の場合は全額免除 申し込み窓口:申請書を提出 URL:「障害者の方に対する受信料の免除」について知りたい|NHKよくある質問集 携帯料金(ドコモ、au、Softbankなど) 割引率:プランにより異なる 活用例:ドコモ ハーティ割引、au スマイルハート割引、Softbank ハートフレンド割引 対象者:全等級の方 上下水道料金 割引・値引き:地域...

補聴器を買うべき?買わないべき?補聴器を始めるタイミングについて
難聴の自覚と、困っている自覚は別のこと。 私たち、大塚補聴器へご相談に来るお客様には2つのパターンがあります。ご本人の意思で来店する場合と、ご家族の強い勧めで来店する場合です。 ご自分の意志で相談に来る方は軽度難聴が多く、また補聴器がすぐに活躍する。 ご本人が自分の意志で来店される方の多くは、具体的な困りごとを持っていらっしゃいます。 例えば 「仕事で上司やお客様の言葉が聞き取れない」 「ダンスや音楽の習い事で先生の話がハッキリしない」 「お芝居を観に行ったときに、ステージから遠くてセリフが分かりにくい」 「病院の診察で、医師の声がハッキリ聞き取れない」 などです。 またご家族に連れてこられる方と比べると、平均60歳代と若く、軽い難聴である場合が多いのです。みなさん「まだ補聴器は早いかも知れないけど、ちょっと困るから話を聞いてみたい」と言って、ご相談にいらっしゃいます。 こういったお客様の...
あなたに合った「聞こえ方」を
一緒に見つけませんか?


