実は高齢者の半分以上が該当!感音性難聴って? 耳に明らかな病気のない方を対象に、年齢ごとの平均聴力を調べた研究1)があります。 その結果、個人差はありますが、なんと70歳後半では概ね2人に1人が難聴だという事がわかりました。 加齢による聞こえにくさは、誰にでも起こる可能性があるのです。 年齢にともなう難聴を加齢性(老人性)難聴といいます。これらは感音性難聴と呼ばれるものの1つです。 感音性難聴は、耳の奥の部分に損傷が起こり、音や言葉が聞こえにくくなる難聴です。下の画像の「蝸牛」や「聴神経」のどちらか、または両方にダメージがあります。蝸牛や三半規管など、耳の奥にある器官をまとめて「内耳」と呼びます。 なお脳のダメージによって聞こえにくくなった場合も、感音性難聴に分類される場合があります。たとえば脳梗塞の後遺症などです。これは人間が音や言葉を認識するためには、耳だけでなく脳も正常に機能している […]
私たち大塚補聴器は、補聴器の専門家として、
一人ひとりのお客様に合った補聴器を選ぶお手伝いをしています。
補聴器に関してよく読まれている記事をまとめています。

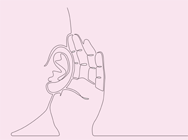
難聴に種類ってあるの?難聴の基本

集音器は、あなたの難聴を助けてくれる?
補聴器と集音器の価格の差 家電店や通販で気軽に買える集音器は、耳鼻科の補聴器外来や補聴器専門店で販売されている補聴器と比べて、価格がまったく違います。補聴器を専門店で購入すると、平均的に片耳で15~20万円ほどですが、集音器は数千円から最高額なものでも80,000円ほどです。 補聴器が高額になる理由と、集音器との違い 価格に関する補聴器と集音器の違い 補聴器が集音器より高額になる理由は、下記のとおりです。 ・集音器と補聴器では、補聴器の方が高額な分だけ高性能。(ただし低価格な補聴器(60,000円程度)と、高級集音器(60,000円程度)の性能の差は、あまりありません。) ・補聴器には聴力測定のためのコストが含まれる。(家電店の棚よりも、専門の防音室などの設備は高額です) ・補聴器調整のための専門家の人件費が含まれる(耳鼻科の医師。言語聴覚士、認定補聴器技能者です) 補聴器と集音器のどちら […]

取り扱いが簡単なオススメ補聴器
補聴器は形が選べます 補聴器は、メーカーや器種、形状も種類があります。耳かけ型、耳あな型と大きく分かれますが、それぞれに取り扱いが簡単な器種があります。 ※耳の形や聴力によっては、オススメできないこともあります。詳しく知りたい方は、ぜひご来店・ご相談ください。 取り扱いが簡単なオススメ補聴器TOP3 ≪ 取り扱い簡単! ≫第1位 スターキー「リビオ充電式耳あな型」 取り扱いが簡単な補聴器をお求めの方へ、一番オススメなのが、スターキー社の「リビオ充電式耳あな型」です。 オーダーメイドの耳あな型補聴器で充電式タイプは、2022年1月現在、他メーカーにはありません。 リビオの充電式耳あな型が登場するまでは、電池交換がネックになっていた方も、安心して耳あな型を選択できるようになりました。 時々、補聴器販売員でも誤解している人がいますが、実は耳あな型の補聴器は、耳かけ型の補聴器より取り扱いは簡単です […]

「最適な出力の補聴器」が「良い補聴器」
補聴器の価格と、音の大きさは関係ありません 補聴器の価格は2万円程度のリーズナブルなものから、100万円以上と高価なものまで、様々です。 しかし補聴器の価格の差は、補聴器の形であったり、機能の違いです。 高額な補聴器では大音量が出るというわけではなく、価格とパワーは関係ありません。 こちらの記事もご参照ください。高い補聴器と安い補聴器の違いとは? 大きな音ならよく聞こえるということはありません 難聴の程度は軽度・中程度・高度・重度など四段階で分類され、 補聴器は難聴の程度に合わせて選ぶ必要があります。 重度難聴の方は、中等度難聴用の補聴器では聞こえません。 重度難聴の方には、重度難聴用のハイパワー補聴器が必要です。 (ここでいうパワーとは、補聴器の最大音量とお考えいただければと思います) 軽度難聴の方が重度難聴用のハイパワー補聴器を使うとよく聞こえません。 重度難聴用のハイパワー補聴器は、 […]

補聴器の調整ってなに?
補聴器の調整ってなに? 補聴器の「調整」とは、お客様に合わせて聞こえやすいように、補聴器を調整していく作業のことを言います。難聴の種類や聴力のレベルによって、試聴する補聴器を選定し、お客様の使用環境に合わせられるようカウンセリングをしながら、聴こえの調整を行います。 調整って音の大きさ調整するの? 補聴器には大きく分けて3つの調整があります。この3つのバランスが良いと、聞こえやすくて疲れにくい補聴器に仕上がります。 ●難聴の聞こえは進行すればするほど、小さい音が聞き取れなくなります。この小さい音を聞き取ることができるように、音を大きくすることを「利得調整」と言います。 ●音を大きくすると、今まで聞こえていなかった雑音がうるさく感じたり、音が響いたりして、かえって聞き取りが悪くなることがあります。また、その人が不快に感じる音の大きさ(不快閾値)よりも大きい音が補聴器から出力されると、とても不 […]

補聴器購入に介護保険が使える?行政の補助はある?
介護保険が使えない理由は、厚生労働省 「補聴器は、高齢者に必要な道具なのだから、介護保険を使えたっていいじゃないか!」と思いますよね。私たちも、そう思います。そこで補聴器と介護保険、両方を管轄している厚生労働省の発行した資料を調べてみました。 介護保険を管轄しているのは、厚生労働省<老健局> まず介護保険について調べてみると、厚生労働省老健局が担当部署でした。そして福祉用具を介護保険に含めるかを判断する会議は「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」といい、なんと毎年開催されています。会議の結果によっては、もしかして補聴器購入にも介護保険が使えるのでしょうか? 介護保険における福祉用具・住宅改修の範囲の考え方! この検討会の中で、やはり毎年引用されている資料に「介護保険における福祉用具・住宅改修の範囲の考え方」というものがあります。補聴器購入の介護保険利用、せめて議論くらいされていて欲しいも […]

耳が遠い方に通じやすい話し方のコツ
それでは一つずつ見ていきましょう。 視線のコツは、相手の顔を見て、視線をもらうこと。 相手の顔を見る効果 人と話をするときに相手の顔を見てお話しするのは、幼稚園でも習う当たり前のマナーですが、これは耳の遠い人にとって、とても助かることです。顔を見て話してくれると、声がまっすぐ飛んできます。またあなたの口の動きが、よく見えると、相手は無意識に口の動きを読んで、言葉を推測することができます。 まずはしっかり意識して、相手の顔を見て、顔を見たまま話しましょう。 視線をもらうことの効果 次の工夫は、相手の視線をこちらに向けてもらうことです。人間は、目で見ているものに対して、無意識に集中力が高まります。逆に、視線を向けていないものに、集中することは困難なのです。 耳が遠い方にとって、人の言葉を聞き分けることは、集中が必要な難しい作業です。その負担を減らすために、視線をこちらに向けてもらいましょう。 […]

補聴器の寿命は5年!寿命をのばすための《メンテナンス・クリーニング》
補聴器は安い買い物ではありません。よく聞こえる補聴器は、長く使い続けたいですよね。 補聴器の寿命の目安となるのは、行政で決められている「耐用年数」です。 「耐用年数」とは、補聴器にかぎらず、エアコンや冷蔵庫、自動車などにも定められており、 機械がどの程度の期間、正常に使うことができるかの目安になります。 補聴器の場合は、耐用年数5年です。 *エアコン・冷蔵庫の耐用年数は6年です。 しかし、これはあくまで目安です。 家電製品も耐用年数(6年)より長く使う方も少なくありません。 補聴器の寿命を伸ばすための、3つの方法をご紹介します。 日々のクリーニングで、寿命は伸びる 専門店のクリーニングで、寿命は伸びる メーカーのメンテナンスで、寿命は伸びる 日々のクリーニングで、寿命はのびる 実際に1台の補聴器を10年以上、使い続けているお客様がいらっしゃいます。 その方が実践しているクリーニング方法をご […]

初心者のための補聴器の選び方・買い方
目立たない補聴器と、取り扱い簡単な補聴器。希望にあった補聴器の<形の選び方> 補聴器には目立たない補聴器、取り扱いが簡単な補聴器など、様々あります。目立たない補聴器は、形が小さくなります。取り扱いが簡単な補聴器は、形が大きくなります。補聴器には、一般的には4つの形があり、それぞれに良いところがあります。 また特殊な補聴器についてもご紹介します。 小型耳あな型補聴器 小型耳かけ型補聴器 耳かけ型補聴器 箱型補聴器 外から見えない小型耳あな型補聴器(IICタイプ) 世界で、もっとも目立たない種類の補聴器で、スポーツなど活発に楽しむ方が、好んで選ばれます。2010年に販売が開始されたもので、形状の種類としては最新型です。 汗に強く、ジムなどでスポーツしながら補聴器を使いたい方にはぴったりです。またゴルフや釣りなど風が吹く環境で、余分な風の音が入りにくくなっています。 ただし形状が小さく、取り扱い […]

補聴器は定期的に掃除する必要があります。
補聴器は定期的に掃除する必要があります。 補聴器は、耳の穴に入れる道具です。そのため補聴器の音口(音の出口)は自然と耳垢で汚れます。 そして、ひどい場合には耳垢で補聴器の音口をふさいでしまう場合がございます。 当然、音の出口がふさがってしまうと音は小さくなり、最後には音が出なくなってしまいます。 これを防ぐためには、補聴器は定期的に掃除する必要があります。 補聴器のお掃除は、器種によってそれぞれ違いますが、日々の管理が難しいということはありません。 目安としては、一週間に一度程度、専用のブラシで補聴器を軽くブラッシングすると汚れが取れます。 また、当店でご購入頂いた補聴器は、ご来店頂ければ、いつでも無料で補聴器のお掃除をいたします。 聞こえの困りごとは、いつでも何でもプロショップ大塚へご相談下さい。
よく読まれている記事

キャッシュレス・消費者還元事業は補聴器も対象。しかも消費税は非課税!
2020年6月まで期間限定のキャッシュレス・消費者還元事業 キャッシュレス・消費者還元事業(キャッシュレス・ポイント還元事業)とは、10月1日の消費税増税にともない経済産業省が実施している施策です。 この事業に加盟した販売店で、お買い物するときにクレジットカードなどの現金以外のお支払い方法を選べば、お買い上げ金額の5%(もしくは2%)が、ポイントとして返ってくる制度です。クレジットカードの種類によっては、引き落とし金額が5%引きになることもあります。 還元率が5%になるのは、中小企業・小規模事業者だけです。コンビニなどの大企業での還元率は2%です。 (例1:普通のお買い物)5%還元のとなる中小企業の販売店で11,000円分(税込)のお買い物をすると5%にあたる550円分がポイントとなって還元されます。 (例2:補聴器のお買い物)5%還元のとなる補聴器専門店プロショップ大塚で300,000円...

補聴器を安く購入するための補助金・助成金・医療費控除・保険適応について
補聴器を購入するにあたって、行政の支援や補助金はないのですかと、ご相談を受けることがございます。 たとえば、平成25年に施行された「障害者総合支援法」により、補聴器の購入費用に対して補助金が支給されるようになりましたし、補聴器の購入に対して助成を行っている自治体もございます。 そこで補助金など、補聴器を少しでも安く購入できるための方法をご紹介させていただきます。 総合支援法による補助金制度 障害者総合支援法という法律が、平成25年4月1日から施行されました。 この法律は身体障害者福祉法も包括されたもので、この新しい制度により補聴器の購入費の補助金が支給されるようになりました。 補聴器を購入する際の補助金を受けるためには、まず障害者総合支援法による障害者手帳が必要となります。 \補聴器支給までの流れ/ ❶身体障害者手帳の取得 ・指定の耳鼻咽喉科判定医の検査を受け、「手帳交付の意見書」を交付し...
補聴器の購入は補助金がもらえる?申請は耳鼻科と自治体への相談が大切
※プリントしてご利用したい方は、下のボタンから概要をまとめた「資料:申請手続きの流れ」(A4資料)がダウンロードできます。資料は、A4の紙1ページにまとめてあります。ご自由にご利用ください。 「資料:申請手続きの流れ(2025年1月更新)」(A4資料)をダウンロードする あなたの聴力は、手帳が該当する? 1.聴覚の身体障害者手帳を申請する流れ! 1-1 耳鼻咽喉科の身体障害者福祉法指定医師を見つける。 「指定医師ってなんだ?」と思いますよね。身体障害者手帳の発行は、行政の制度です。そのため手帳発行については、地域の行政機関と連携している医師に相談する必要があります。市役所の福祉課などへ相談すれば、耳鼻咽喉科の身体障害者福祉法指定医師を教えてもらえるでしょう。自治体の窓口を訪れるのが難しい場合は、電話やFAXで、自分の住所を職員に伝えて、一番近くの指定医師を教えてもらいましょう。 ※本人の体...
あなたに合った「聞こえ方」を
一緒に見つけませんか?


