ただ「音を大きくする」補聴器では、もう足りない 補聴器を使っていても「聞こえているはずなのに、言葉が頭に入ってこない」と感じることがあります。 これは多くの方が直面している、いわゆる“聞こえるけれど理解できない”問題です。静かな部屋では問題ないのに、駅の構内やにぎやかなレストランに行くと、会話が雑音にかき消されてしまう。誰かと話していても、内容がつかめずにうなずくばかり……。 このような課題は、従来の補聴器が「音を大きくする」ことには長けていても、「どの音を大きくすべきか」の判断には対応しきれていなかったことに起因します。 Edge AIシリーズは、この問題に新しいアプローチを採用しています。AIが常に耳元で働き続け、「聞きたい音」と「聞かなくてよい音」を判断し、あなたの会話をサポートします。 ノイズリダクションの課題|従来技術の限界 従来のデジタル補聴器にもノイズリダクション(MNR: […]
私たち大塚補聴器は、補聴器の専門家として、
一人ひとりのお客様に合った補聴器を選ぶお手伝いをしています。
補聴器に関してよく読まれている記事をまとめています。

補聴器について
補聴器で「よく聞こえる」ようになるには、音に慣れていく“聴覚リハビリ”が欠かせません。私たちは、ご希望や聴力、生活環境に合わせて、無理のない補聴器選びをお手伝いしています。
このページでは、補聴器の選び方や補助金制度など、よくいただくご相談をまとめています。
Edge AIシリーズ:静かさと会話を両立する補聴器の新基準
【千葉県】補聴器の助成制度について解説!
【目次】お住まいの自治体の助成制度をチェックしましょう 千葉県内市町村一覧 ※市町村名をクリックすると該当の市町村に移動します。 旭市 我孫子市 いすみ市 市川市 一宮町 市原市 印西市 浦安市 大網白里市 大多喜町 御宿町 柏市 勝浦市 香取市 鎌ケ谷市 鴨川市 木更津市 君津市 鋸南町 九十九里町 神崎町 栄町 佐倉市 山武市 酒々井町 芝山町 白子町 白井市 匝瑳市 袖ケ浦市 多古町 館山市 千葉市 銚子市 長生村 長南町 東金市 東庄町 富里市 長柄町 流山市 習志野市 成田市 野田市 富津市 船橋市 松戸市 南房総市 睦沢町 茂原市 八街市 八千代市 横芝光町 四街道市 東京都内23区外市町村一覧 ※市町村名をクリックすると該当の市町村に移動します。 旭市 我孫子市 いすみ市 市川市 一宮町 市原市 印西市 浦安市 大網白里市 大多喜町 御宿町 柏市 勝浦市 香取市 鎌ケ谷市 鴨 […]
【東京23区外】補聴器の助成制度について解説!
東京都内23区外市町村一覧 ※市町村名をクリックすると該当の市町村に移動します。 昭島市 あきる野市 稲城市 青梅市 奥多摩市 清瀬市 国立市 小金井市 国分寺市 小平市 狛江市 立川市 多摩市 調布市 西東京市 八王子市 羽村市 東久留米市 東村山市 東大和市 日野市 日の出町 府中市 福生市 町田市 瑞穂町 三鷹市 武蔵野市 武蔵村山市 青ヶ島村 大島町 小笠原村 神津島村 利島村 新島村 八丈町 御蔵島村 三宅村 東京都内23区外市町村一覧 ※市町村名をクリックすると該当の市町村に移動します。 昭島市 あきる野市 稲城市 青梅市 奥多摩市 清瀬市 国立市 小金井市 国分寺市 小平市 狛江市 立川市 多摩市 調布市 西東京市 八王子市 羽村市 東久留米市 東村山市 東大和市 日野市 日の出町 府中市 福生市 町田市 瑞穂町 三鷹市 武蔵野市 武蔵村山市 青ヶ島村 大島町 小笠原村 神津 […]
【東京23区】補聴器の助成制度について解説!
東京都内23区一覧 ※クリックすると該当の自治体に移動します。 足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 品川区 渋谷区 新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区 練馬区 文京区 港区 目黒区 東京都内23区一覧 ※クリックすると該当の自治体に移動します。 足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 品川区 渋谷区 新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区 練馬区 文京区 港区 目黒区 足立区の補聴器助成金 助成金額上限 50,000円 対象者条件 次のすべてに当てはまる方 区内に住所を有する満65歳以上の方。 聴覚障がいによる身体障害者手帳の対象とならない方。 耳鼻科の医師から意見書が得られる方。なお、基準は下記の通り。 両耳の聴力レベルが40dB以上 […]
総合支援法に対応した補聴器、世界6大メーカーまとめ
聴覚の身体障害者手帳の2~6級をお持ちの方は、お住いの自治体へ申請することで補聴器の購入費用が助成されます。 3級以上が重度難聴用の補聴器、4級と6級は高度難聴用の補聴器の助成が認められます。 補聴器はメーカーによって聞こえ方に違いがあります 総合支援法に対応した一部の機種は、最新補聴器の低価格の器種が、更にお安く手に入り大変お得です。 同時に何年も前の型落ちの補聴器は総合支援法の対象器種になっていることもあり注意が必要です。 世界6大補聴器メーカーの中から、2025年3月現在おすすめの総合支援法の対象器種は次の通りです。 総合支援法“高度難聴用”の おすすめモデル機能表 ※1Android接続に専用のアクセサリが必要です。 フォナック ナイーダ L-30 SP オーティコン G300SC PP スターキー Livio 1000w ITC R ワイデックス RIC 312 D […]
補聴器の購入は補助金がもらえる?申請は耳鼻科と自治体への相談が大切
※プリントしてご利用したい方は、下のボタンから概要をまとめた「資料:申請手続きの流れ」(A4資料)がダウンロードできます。資料は、A4の紙1ページにまとめてあります。ご自由にご利用ください。 「資料:申請手続きの流れ(2025年1月更新)」(A4資料)をダウンロードする あなたの聴力は、手帳が該当する? 1.聴覚の身体障害者手帳を申請する流れ! 1-1 耳鼻咽喉科の身体障害者福祉法指定医師を見つける。 「指定医師ってなんだ?」と思いますよね。身体障害者手帳の発行は、行政の制度です。そのため手帳発行については、地域の行政機関と連携している医師に相談する必要があります。市役所の福祉課などへ相談すれば、耳鼻咽喉科の身体障害者福祉法指定医師を教えてもらえるでしょう。自治体の窓口を訪れるのが難しい場合は、電話やFAXで、自分の住所を職員に伝えて、一番近くの指定医師を教えてもらいましょう。 ※本人の体 […]
フォナック補聴器が新製品「インフィニオ スフィア」を発表。AI専用チップ搭載で、騒音下での聴覚の新境地を目指す
オーデオスフィア インフィニオは、音声と雑音を分離する専用AIチップを搭載した世界初の補聴器 フォナックの新製品「オーデオ インフィニオ スフィア」は、音の増幅や雑音抑制を効果的に行うため、2種類のコンピュータチップを搭載しました。 ERAチップは、旧来の補聴器からあった機能をさらに進化させ、サウンド・クオリティの進化、スマホやテレビとの接続性の向上が図られています。 インフィニオ スフィアから初めて搭載されるDEEPSONICチップは、AIによる言葉と雑音の分離だけに特化した専用チップです。 近年、AIとDNNを用いた補聴器はメーカー各社から登場していますが、完全にAI雑音抑制に特化した専用チップを搭載した補聴器は、インフィニオ スフィアが世界初。 10 dBのS/N比改善という強力な効果が報告されており、騒音下での言葉の聞き取りの大幅な改善が期待できます。 オーデオ インフィニオ スフ […]
Signia ActivePro IX/Active IX発売。お洒落なイヤホン型補聴器!
前作の「Signia Active Pro/Active」は本格補聴器メーカーで初めての充電式レディメイド耳穴型補聴器として好評を博しました。 そんな「Signia Active Pro/Active」で最新チップIXを搭載したモデルが発売されます。シンプルな見た目と高機能を兼ね備えた、カジュアルに使いやすい器種となっています。 Signia Activeは補聴器がはじめての人におすすめ! Active Pro IX/Active IXは、補聴器の使用が初めての方にとてもおすすめです。 「最近、少し聞こえにくく感じる」「常に装着しておきたいが、見た目に違和感がないものが良い」「補聴器を装用していると分かりにくいデザインで、イヤホンのようにカジュアルに使いたい」といったお悩みやご要望に応える製品です。 装着のしやすさとデザイン性、そして聞き取りサポート機能を備えているため、初めての方でも安心 […]
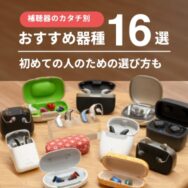
補聴器のカタチ別おすすめ器種16選、初めての人のための選び方も
自分にぴったり合った補聴器を選ぶには? 自分にぴったりの補聴器を選ぶには、いくつかの要素があります。 1、よく聞こえるようにしたい場面から選ぶ 補聴器を考え始めたキッカケを思い出してみましょう。 たとえば、友人たちが冗談で笑っている時に、自分だけ聞き逃してしまい笑えない。それが何度も続くなら”何とかしたい”と思うものです。 補聴器は、よく聞こえるようにしたい場面に合わせて、必要な機能が搭載されている器種を選ぶのがおすすめです。 補聴器は音を大きくするだけではなく、言葉の聞き取りを補助したり、うるささを減らす機能があります。多機能な補聴器ほどより自然に聞こえやすくなりますが高額になります。必要な機能と予算のバランスをみて、自分にあった器種を選びましょう。 2、形から選ぶ 補聴器にはいくつかの形状があり、目立たなさの好み、取り扱いの簡単さのご希望によっておすすめのカタチ […]
Widex補聴器からスマートな新製品「SmartRIC」が発売されました。
新デザインで指向性マイクの性能が改善 SmartRICでは旧製品からデザインが刷新されました。今回のデザインの変更は見た目だけではなく、補聴器の機能にも大きく影響を与えています。 補聴器本体のデザイン SmartRICではデザインが刷新されました。 これまでの耳掛け型補聴器と異なり、本体が細くスマートになっています。 この本体のカーブは人間の耳の上部のカタチに合わせて設計されており、補聴器本体の重心が低い位置になるので、補聴器を付けたまま活発に動いた時も着け心地が安定するようになりました。今まで以上に耳にぴったりフィットします。 新型マイクにより雑音下での聞こえが改善 SmartRICでは雑音と言葉を分ける機能が改善されました。 補聴器に搭載されているマイクの角度が水平になったことで、補聴器をつけた人が顔を向けている方向の音を優先して拾う機能(指向性)が働きやすくなりました。 雑音のあると […]
よく読まれている記事

補聴器購入に介護保険が使える?行政の補助はある?
介護保険が使えない理由は、厚生労働省 「補聴器は、高齢者に必要な道具なのだから、介護保険を使えたっていいじゃないか!」と思いますよね。私たちも、そう思います。そこで補聴器と介護保険、両方を管轄している厚生労働省の発行した資料を調べてみました。 介護保険を管轄しているのは、厚生労働省<老健局> まず介護保険について調べてみると、厚生労働省老健局が担当部署でした。そして福祉用具を介護保険に含めるかを判断する会議は「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」といい、なんと毎年開催されています。会議の結果によっては、もしかして補聴器購入にも介護保険が使えるのでしょうか? 介護保険における福祉用具・住宅改修の範囲の考え方! この検討会の中で、やはり毎年引用されている資料に「介護保険における福祉用具・住宅改修の範囲の考え方」というものがあります。補聴器購入の介護保険利用、せめて議論くらいされていて欲しいも...

【コロナウイルス】感染拡大防止への取り組み(お客様と従業員の感染防止に最善を尽くします)
プロショップ大塚の衛生管理について スタッフは常時マスクを着用します。 店内では、スタッフは常時マスクを着用します。 口元が見えないと会話できないお客様の場合、透明マスク、フェイスシールドおよび筆談のご用意があります。 ご来店されたお客様には全員マスク着用をお願いします。 マスクをお持ちでない方はお渡しします。 ご来店されたら、まず消毒液をご利用いただきます。 スタッフも各所に消毒液を配置し、こまめに使用しています。 接客カウンターには、透明アクリル板をご用意しております。 完全予約制でご対応します。 当分の間、完全予約制でご対応いたします。 お客様同士で感染することを避けるため、お客様が同じ時間に重ならないようにいたします。 直接、店舗に電話で予約する 予約する店舗が決まっている方は、直接 各店舗に連絡をしていただくのが一番確実です。 パソコン/スマホから予約する 接客毎に消毒します。 ...

難聴レベルってなに?聴力検査の結果(オージオグラム)の見方
聴力検査の結果は、オージオグラムという図で表します。病院で聴力検査を受けた方は、もしコピーをいただけるようならお願いしてみて下さい。 オージオグラムからわかること まずはオージオグラムの基礎や、オージオグラムからわかることについて、ひとつずつ見ていきましょう。 オージオグラムの基礎 オージオグラムとは、あなたの聴力検査の結果を図で表したものです。聴力検査を受けるときにはヘッドホンをつけて、音が聞こえたらボタンを押す、または手を上げる方法で行います。この検査では、あなたが聞こえるギリギリの音の大きさを調べ、これを数値で表しているのです。 上の図はオージオグラムの一例です。表の見方と記号を説明します。記号の「○」は右耳、「×」は左耳を表しています。 縦軸は、音の大きさ=聴力レベル(dB:デシベル)を表しています。表の縦軸の目盛りをみると、-20dB〜120dBまで数値があります。音の大きさは数...
あなたに合った「聞こえ方」を
一緒に見つけませんか?


