オトスキャン(otoscan)とは? オトスキャンは、世界初の3Dデジタルイヤスキャナーです。レーザーを用いて、非接触で耳の形状を立体的に撮影することが出来る装置になります。 これによってオーダーメイドの耳あな型補聴器やオーダーメイドの耳せん(イヤモールド)のご注文をいただいた際、お客様への負担を減らし、耳の病気やケガの経験者の方には今まで以上に安全になり、より良い補聴器が作れるようになりました。 オーダーメイドの耳あな型補聴器やオーダーメイドの耳せんを作るとき、これまでは下の画像のような手法がありました。 オトスキャンでは、下の動画のようにレーザーで耳の形状を撮影します。耳型そのものは採取しません。 実際にオーダーメイドの補聴器を作る場合、必ずしも耳型は必要ありません。補聴器は、耳の立体形状のデータだけあれば作れるので、オトスキャンは3D形状データを直接撮影しているのです。 オトスキャン […]
私たち大塚補聴器は、補聴器の専門家として、
一人ひとりのお客様に合った補聴器を選ぶお手伝いをしています。
補聴器に関してよく読まれている記事をまとめています。


耳の3D形状撮影装置オトスキャン(Otoscan)を全店に導入しました。

難聴の原因になるメニエール病とこれに対応した補聴器について
メニエール病って、どんな症状? 原因は? 再発するの? メニエール病は、めまいを伴う耳の病気で、難聴の原因にもなります。初期の主な症状は、世界が回って感じる回転性のめまいと、片耳の難聴・耳鳴り・耳の閉塞感があります。ほとんどの人は、なんの前触れもなく症状が起こり、吐き気を伴うこともあります。 めまいは発作的で、10分から数時間ほど持続します。この時間の間は立っていることもままならず、じっと横になっていることしかできません。 数時間ほど経過すると一時的な難聴や耳鳴りの症状はおよそ回復します。しかし発作を何度か繰り返すと、少しずつ聴力が低下していきます。 メニエール病の原因は、ストレス? メニエール病が発症する原因は、まだ解明されていません。 しかし、メニエール病にかかりやすい人の傾向は分かってきており、具体的には30~50歳代の女性が多く発症すると言われています。 そのため、メニエール病にか […]

値段がお安い補聴器のご紹介「リサウンド・キー」
値段が安くておすすめの補聴器紹介コーナー! 当社では世界の6大補聴器メーカーから、安くておすすめの補聴器をご紹介してきました。今回はGNヒアリング社の「リサウンド・キー」シリーズから、他社になく、特徴的な補聴器をピックアップします。 なお、どのメーカーでも値段が高くなれば、高機能になるのは当たり前です。 値段が安い補聴器から自分にピッタリあったものを見つけるには、たくさんのメーカーの中から探すことがおすすめです。 当社のWebサイトでは、各メーカーで、お安い補聴器の紹介記事を出しています。ぜひご一読ください。 ご予算に合った補聴器をお探しの方は、ぜひご相談ください。 小さい耳あな型補聴器でもイヤホンのように音楽が聞ける「KE3CIC-W」 KE3CIC-Wは、リサウンド・キーの中で、1番小さく、目立ちにくい耳あな型補聴器です。 着けている時に前や後ろから気づかれることはありません。横からの […]

聴力検査の種類とそれぞれの見方
健康診断の聴力検査は、難聴の予兆を見つける選別聴力検査 会社などで受ける健康診断の一つに聴力検査の項目があります。 健康診断の聴力検査のことを正式には「選別聴力検査」と言います。多くの方が一度は経験したことのある聴力検査だと思います。 この検査は、聞こえの問題があるかも知れない人や、難聴の予兆がありそうな人を早期に発見するために実施されています。耳鼻科で受ける検査に比べると、難聴の原因など具体的なことは分かりませんが、短時間で終わることが特徴です。 選別聴力検査の具体的な流れは次のようになっています。 ①ヘッドフォンをつける。 ②ピーピーという音(1000Hz)が聞こえてくる。聞こえたらボタンを押す。もしくは手をあげる。 ③キーキーという音(4000Hz)が聞こえてくる。聞こえたらボタンを押す。もしくは手をあげる。 ④検査する人は、2種類の音それぞれで、一定以下の小さな音が聞こえるか、聞こ […]
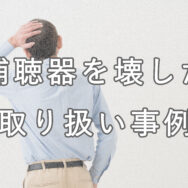
取り扱いのうっかりミスが原因で、補聴器が故障する事例と対処法
取り扱いのうっかりミスで、補聴器が故障する原因になること 補聴器は、毎日使うものです。毎日のことですから、誰でも一回や二回はまちがえた取り扱いをすることがあります。まちがえた取り扱いに気づかず使い続けると、故障につながる場合があります。この記事では補聴器が故障する原因になる取り扱いの事例と、それらの対処法もご紹介いたします。 電池の極(プラス/マイナス)を逆にして、無理やり電池カバーに入れてしまう 補聴器に電池を入れるとき、プラス/マイナス極(+/-)を逆にして、電池カバーを閉めてしまうことがあります。もちろん音は出ません。これが補聴器の故障につながることがあります。 電池のプラス/マイナス極を逆に入れると、補聴器から音が出なくなる 時々、数人の方から「新しい電池を入れたばかりなのに、補聴器から音が聞こえなくなった」「買ったばかりなのにもう壊れた」という声を聞きます。 補聴器を見せていただ […]

補聴器の種類によるメリットの違い【耳かけ型・耳あな型】
【耳かけ型・耳あな型】補聴器の特徴・メリット 補聴器の種類は「耳かけ型」「耳あな型」の2つが主流で、全販売数の90%以上を占めています。両方とも、内部の構造は同じです。選んだ種類によって、つけ心地や見た目が変わります。また音質や機能にも少し違いがあります。 マスクの邪魔にならない耳あな型補聴器 耳あな型補聴器は、本体が耳の穴にすっぽり収まるタイプ。すべての部品が小さい本体に収まっています。オーダーメイドが一般的ですが、一部既製品もあります。 価格は95,000円~600,000円ほど。従来電池交換式のみでしたが、一部充電式のタイプも出始めています。 コロナ感染流行以降、マスクをかけることが日常的になりました。そのためマスクと干渉ない耳あな型の人気が高まっています。 昔ながらの形の耳かけ型補聴器 耳かけ型補聴器は昔から人気がある種類です。「目立ちやすい」というイメージがあるようですが、近年小 […]

補聴器の種類、見た目とサイズがわかる画像つき
耳あな型補聴器の種類を画像で比較! ・IIC(極小サイズ) 外から着けていることがまったく見えません。1円玉より小さく耳の奥、鼓膜の近くまで入ります。軽度~中等度難聴に対応します。 ・CIC(小さいサイズ) IICと同じく耳の奥深くに入るので、顔の横や後ろから見てもほとんど気づかれません。1円玉と同じくらいのサイズです。形状は小さいですが、高度難聴まで対応できます。 ・カナルサイズ(標準) 最も普及している定番サイズ。指先の動きの関係でIIC、CICサイズの取り扱いが難しかった方にもお使いいただけます。カナル以上のサイズからは、追加でさまざまな機能がつけられます。 ・ハーフシェル(少し大きいサイズ) カナルよりも見た目がやや大きくなります。外から見えますが取り扱いが最も簡単で、高機能です。軽度から高度難聴まで幅も広くなります。耳穴の入り口にフィットするので安定感があり取り扱いやすいサイズで […]

値段が安いシグニアのオススメ補聴器を紹介
シグニア補聴器の特徴はこちら シーメンス・シグニア補聴器の特徴は、補聴器をタンスの肥やしにした人(使わない人)にこそ合う シグニアのお買い得補聴器「Intuis3」と「1Nx」 今回は、シグニア補聴器の中でも値段が安く、お買い得な補聴器を厳選してご紹介します。 Intuis3は、シグニアの中でもお安く、様々な形状が選べるシリーズです。耳かけ型は片耳90,000円から販売されており、特におすすめです。 Intuis3の耳かけ型は5種類の形状から選べます。 Intuis3の耳あな型は片耳110,000円〜。形状は4種類から選べます。 1Nxは多機能搭載タイプの補聴器としては、もっとも安い器種です。片耳10万円台の低価格ながら、充電式やBluetooth機能など、便利な機能が多数搭載されています。1Nxは好みの見た目・デザインに合わせて、耳かけ型6種類、耳あな型6種類から選べます。 この記事では […]

突発性難聴の症状、ストレスが原因?治る可能性は?
突発性難聴の症状 突発性難聴は、片耳が突然聞こえにくくなる病気 突発性難聴はその名のとおり突然聞こえが悪くなる病気です。一般的に片耳のみに発症し、一度発症すると再度発症することはないといわれています。聞こえにくさの度合いは人によって様々で、ごく軽い難聴のこともあれば重度の難聴になってしまうこともあります。 突発性難聴の症状(前兆)4つ 突発性難聴は難聴だけでなく、他の症状が発生し、そちらが先に気になることもあります。初期症状(前兆とも言います)に気づいたときは見逃さず、すぐ耳鼻科を受診しましょう。突発性難聴だった場合、早期に治療を開始することで完治する可能性が高まります。 感じ方は個人差があるので、実際に突発性難聴になった方の言葉を紹介します。 ①「耳がこもった感じ」「詰まった感じがする」 突発性難聴の初期には「聞こえにくくなった」という感想ではなく「こもった感じ」や「詰まった感じ」が生じ […]

聴力低下と難聴は別物!-年齢による聴力低下はいつから始まる?-
聴力低下は20代から! 私たち聴覚の専門家は、お客様から「耳って何歳から遠くなるの?」というご質問をいただくことがあります。 実は、聴力低下は20代から始まってしまうのです。 この話を聞くと皆さん驚かれます。しかし実際には不安に思われるような大きな問題ではありません。 聴力が低下し始めることと、難聴によって会話が困るようになってしまうことは、全く違うのです。 20代から聴力が低下し始めるというのは、人生で体力のピークが20歳前後にあるのと同じことです。少しずつ体力が落ちたり、走るのが遅くなるのと同じように、耳の聞こえも少しずつ低下していきます。 この聴力の低下は、普通に生活している時には、自覚することが出来ないほど緩やかな変化です。20~30歳台の頃に聞こえにくさを感じることはほぼ無いでしょう。 聴力低下がある程度進むと難聴となり、聞こえにくさを感じるようになります。 聞こえに困るほどの難 […]
よく読まれている記事
補聴器から変な音がしても、音源が分かると安心する話
原因不明の音源はどうするの? 基本的に補聴器で久しぶりに音が聞こえても、不快でなければ(耳のいい人が聞こえている音なら)聞こえることは良いことです。 でも、まれに「なんの音か分からないけど、音が聞こえて気になる!」という訴えをいただくことがあります。音源が見つけられないと気になってしまうんですよね。 今まで一番難しかった音源探し 今までで一番難しかったのは「いつもじゃないけど、定期的にゴーって音が聞こえる。かなり大きいけど1~2分で止まる。洗濯機や食器洗い乾燥機は動かしてない。いつも時間が決まってる」というもの。 お話をうかがっても音源が分からず、補聴器にも異常なく、ご自宅までうかがって10分ほどしたら分かりました。 音源は新幹線の走行音でした。 在来線も並走しているんですが、そっちは補聴器のノイズキャンセリングのおかげでまったく気付かず、でも新幹線の音は線路が近いこともあって聞こえていた...
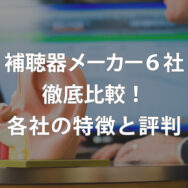
2025年:補聴器メーカー各社の特徴と評判、上位6社を徹底比較
補聴器の人気メーカーの比較と特徴 補聴器は一人ひとりの聴力を測定して、耳の状態に合わせて音質を調整するものです。しかしメーカーごとに調整で変えられない特徴があります。本記事では調整で変えられない特徴や評判を比較していきます。 多くの補聴器メーカーは、製品ブランド名と会社名が異なります。 本記事では、ブランド名を表記しています。なおカッコ内には国内の販売代理店ではなく、製品開発元の社名を記載しました。 オーティコン オーティコンは、北欧のデンマーク王国に本社を置く補聴器メーカー「デマント社」が展開する補聴器ブランドです。 オーティコンの補聴器は「Brain Hearing(脳で聴く)」をコンセプトに開発されています。デマント社は、耳だけでなく脳についても独自に研究を行い、その結果を活かして補聴器を開発しています。 2016年に発売されたOpn(オープン)シリーズから、他社とはまったく異なった...
フォナック補聴器が新製品「インフィニオ スフィア」を発表。AI専用チップ搭載で、騒音下での聴覚の新境地を目指す
オーデオスフィア インフィニオは、音声と雑音を分離する専用AIチップを搭載した世界初の補聴器 フォナックの新製品「オーデオ インフィニオ スフィア」は、音の増幅や雑音抑制を効果的に行うため、2種類のコンピュータチップを搭載しました。 ERAチップは、旧来の補聴器からあった機能をさらに進化させ、サウンド・クオリティの進化、スマホやテレビとの接続性の向上が図られています。 インフィニオ スフィアから初めて搭載されるDEEPSONICチップは、AIによる言葉と雑音の分離だけに特化した専用チップです。 近年、AIとDNNを用いた補聴器はメーカー各社から登場していますが、完全にAI雑音抑制に特化した専用チップを搭載した補聴器は、インフィニオ スフィアが世界初。 10 dBのS/N比改善という強力な効果が報告されており、騒音下での言葉の聞き取りの大幅な改善が期待できます。 オーデオ インフィニオ スフ...
あなたに合った「聞こえ方」を
一緒に見つけませんか?


